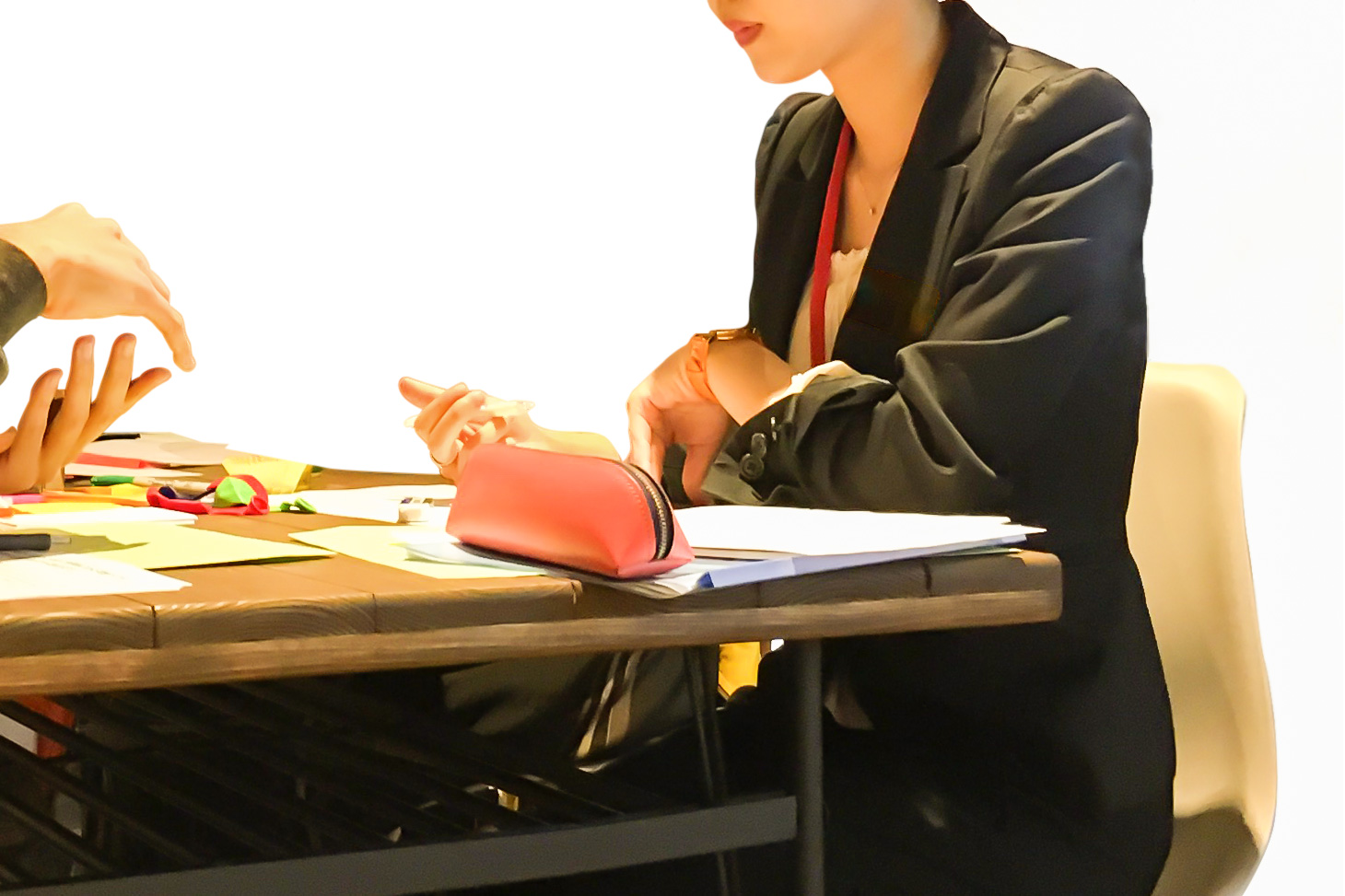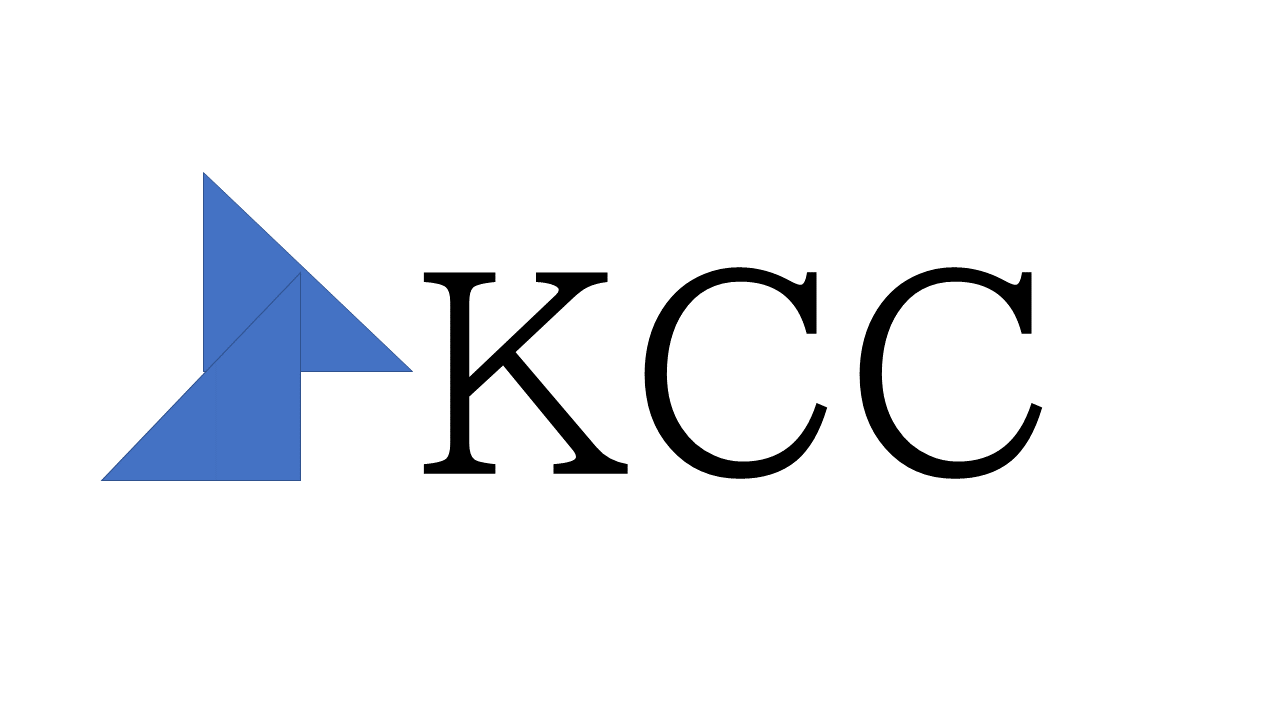「AIのせいで、ライターの仕事はなくなるかもしれない」「AIを使えば、面倒な作業から解放されて仕事が楽になるはずだ」――(生成)AIと聞いて、あなたはこのように考えたかもしれません。ライターなら誰もが一度は、この新しいテクノロジーに期待と不安が入り混じった複雑な感情を抱いたことがあるはずです。もしかしたら、まるで魔法の杖のように完璧な文章を一瞬で生み出す、奇跡のような存在、同時に、ライターとしては悪夢のような存在と捉えたかもしれません。
しかし、実際にAIと向き合ってみると、そのどちらとも違う「リアルな姿」が見えてきます。残念ながら、AIは世間で言われているほど万能ではありません。本記事では、「AIはライターに代替するのか?」という問いに対し、「代替はしない。しかし、働き方は確実に変わる」という視点から、AIとの新しい付き合い方を提案します。AIを恐れるのではなく、かといって盲信するでもなく、上手に使い賢く付き合うためのヒントを紹介します。
目次
その期待と不安は実現しない? AIライティングの不都合な真実
多くの人がAIに抱くイメージは「魔法の杖」かもしれません。キーワードをいくつか入力すれば、ものの数秒で完成度の高い文章が生成される――そうした夢のようなツールだと思われがちです。しかし、現実は決してバラ色ではないのです。
AIが生成した文章は、一見すると流暢で説得力があるように見えます。しかし、よく読んでみてください。本当にその文章は「完璧」でしょうか。きっと違うでしょう。冗長だったり言葉足らずだったりで、とてもそのまま使えません。間違いも少なからずあります。平気で嘘をつき、文脈を無視し、場合によってはユーザーの指示も無視します。
結局、人間がファクトチェックを行い、不自然な言い回しを修正し、文章全体のトーンを整えます。手直しに没頭しているうちに、気づけばゼロから自分で書いた方が早かった、という経験をしたことも少なからずあるのではないでしょうか。特に、AIがもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」と呼ばれる現象は厄介。10個のうち9個は本当で1つだけ間違っていた、なんてこともざらです。しかも、「これはどこそこに載っていたので間違いありません」と堂々とウソをつくので、その見極めには専門的な知識と注意力が必要になります。
また、AIは「空気が読めない」「流れを読まない」という弱点を抱えています。例えば、取材記事を作成する際に、取材相手が「これはあまり積極的に公表はしていないのですが」と前置きをしたとします。人間であれば、そのニュアンスを汲み取り、表現をぼかしたり、あえて書かなかったりという判断をします。しかし、AIはそのような配慮ができません。重要な情報だからこそ、遠慮なくストレートに文章化してしまう可能性があります(きっと多くの場合そうするでしょう)。言葉の強弱や繊細なニュアンスを調整し、人間関係に配慮しながら言葉を紡ぐ。これは、少なくとも今のAIにはできません。人間にしかできない高度なコミュニケーションなのです。
AIはプロライターの仕事を奪うか?――クラウドソーシングとの類似点
AIはライターの仕事を奪うのでしょうか。結論から言えば、AIがライターに「代替する」ことは、少なくとも当面はないと考えられます。端的に言えば品質が伴わないからです。AIはあくまで文章を生成するツールであり、意思や哲学を持ち経験を積み重ねた「プロのライター」とは異なります。
この状況は、かつてクラウドソーシングが登場したころと少し似ているかもしれません。当時、「プロのライターに頼まなくても、安価で大量に記事が手に入る」と考え、経験の浅い書き手やノンプロに大量発注される動きがありました。その結果として納品されたのは、品質の伴わない記事の山でした。結局、多く場合「安かろう悪かろう」を痛感し、再びプロのライターに仕事を依頼する「回帰現象」が起きました。
AIも同じことが起こるかもしれません。「AIに書かせればコストが浮く」という安易な考えは、いずれ品質の壁にぶつかります。読者の心を動かし、ブランドイメージを向上させる文章は、AIが自動生成しただけのテキストでは実現が難しいからです。最終的には、AIが生成した文章を適切に編集し、魂を吹き込む「生身の人間の感覚」が求められます。このため、ライターが、改めてその価値を評価される時代が来ることも予想されます。ただし、スキルを磨かないライターは淘汰されます。この意味では、AIが仕事を奪うということも言えるかもしれません。
AIは文章を書けます。一見すれば一定品質以上ですが、よく読めば穴がたくさんあります。何度も書き直しに応じてくれますが、思うような文章をなかなか生成してくれません。きっとイライラするでしょう。そもそも、人間がテーマを示し指示(プロンプト)を与えない限りは、書いてくれないのです。もっというと、指示を出すのも一定のスキルが要求されるのです。
AIとの新しい関係性 ――ライターから「編集者/ディレクター」へ
AIが現状、ライターに「完璧には」代替しないとすれば、ライターはAIとどのような関係を築いていけばよいのでしょうか。その答えは、ライター自身の役割を「文章を書く人」から、「文章をディレクションする人」へと進化させることにあると考えられます。
AIと人間の関係は、「ライターと編集者」の関係のようになると推察されます。ただし、熟練のライターとは言い難いので、不器用だけど素直に仕事をしてくれる新人ライターというほうが適切かもしれません。そのAIという新人ライターに対して、人間は編集者やディレクターとして接します。どんな読者を対象として、何を、どのようなトーンで表現するのか。その意図を明確に言語化し、的確な指示を新人ライターに与える。新人ライターが提出してきた原稿を培ったプロの視点で査読し、より良いものへと磨き上げていく。これからのライターにはそのような能力が求められようになっていくでしょう。
最も重要なのは、人間が「意思決定」と「責任」を担うということです。「この記事で何を伝えたいのか、何を成し遂げたいのか」という目的を定めるのは、AIにはできません。納品物に対する最終的な責任を負うのも、言うまでもなく人間です。「AIが書いたので、内容の責任は負えません」という言い訳は、通用しません。ましてプロならなおさらのことです。
AI活用術 ――「効率化」から「質的向上」へ
AIの真価は、「代筆者」あるいは「時短ツール」というよりは「発想支援ツール」として捉えた時に発揮されます。実際にAIを使いこなしているライターの多くは、作業時間の短縮よりも、自身の創造性を刺激される「質的向上」の側面にメリットを感じているようです。
具体的な活用シーンを考えてみましょう。例えば、取材の準備段階で、AIは最高の壁打ち相手になります。自分で考えた質問案を投げかければ、別の角度からの質問を提案してくれたり、想定される回答や、さらに深掘りするためのポイントまで示してくれたりします。一人でうんうんと唸る時間が、創造的な対話の時間に変わるのです。
また、構成案を作成する際にもAIは役立ちます。テーマを伝えるだけで、複数の構成パターンを瞬時に提案してくれます。自分では思いつかなかった切り口や視点に気づかされ、企画の幅が大きく広がることもあるでしょう。表現に行き詰まったときに、自分の文章をAIにリライトさせてみるのも有用な使い方です。マンネリ化しがちな語彙や言い回しを刷新するきっかけを与えてくれます。
AI時代を生き抜くライターの価値とは
AIの登場で、ライターの仕事が大きな転換期を迎えていることは間違いありません。しかし、脅威と捉える必要はないのです。AIを恐れたり、過度に期待したりするのは誤りです。あくまで新しい「道具」であり「パートナー」として、いかに使いこなすかという視点が重要になってきます。初めてインターネットが登場した時、あるいはワープロが出てきた時と似ているかもしれません。
これからのライターには、正しく適切な文章を書く能力はもちろんのこと、その前提となる「企画力」、アウトプットの質を高める「編集力」、AIに的確な指示を出す「ディレクション能力」が、強く求められるようになります。プロとしての哲学や矜持、良い意味での個性も大事になると感じます。AIの生成した文章の良し悪しを判断し、的確な修正を加えるためには、書き手自に確固たる「良い文章」の基準がなければならないからです。何より、「プロとして腕を磨き続ける姿勢」が欠かせません。AIという便利な道具が登場したからこそ、私たちはより一層、語彙力や構成力、表現力などの基礎体力を鍛え、プロフェッショナルとしての審美眼を養い続ける必要があるのです。
忘れてならないのは、AIは経験も体験もできないことです。AIは文章を書けます。一定の品質以上です。小学生や中学生の文章よりは上手かもしれません。言葉遣いも巧みです。ただし、自らの経験や体験から生み出された熱量や思いはないでしょう。
私たちはAIという賢いアシスタントを手に入れました。その結果、これまで以上に創造を発揮できるようになるはずです。新しい技術を巧みに操り、ライターとしての価値をさらに高めていきましょう。
あとがき
最後までお読みいただき、ありがとうございます。この記事で述べたことは、AIと協働することへの現時点での私の一つの考えです。
正直に言えば、私自身もAIが登場した当初は戸惑い、その計り知れない能力に脅威を感じたこともありました。しかし、日々試行錯誤を重ねる中で、AIは敵でもなければ魔法の杖でもなく、あくまで私たちの仕事をサポートしてくれる「優秀な新人ライター」あるいは「有能だけど、時に融通がきかず、扱いにくさもある、少し風変わりなアシスタント」だと捉えるようになりました。
AIの技術は日進月歩で進化しており、1年後もしかしたら1カ月後にはこの記事の内容が古くなっているかもしれません。だからこそ、私たちライターは常にアンテナを張り、新しい技術を学び、変化を楽しみながら自分のスキルをアップデートしていく必要があるでしょう。この記事が、AIとのより良い関係を築くための一助となれば幸いです。