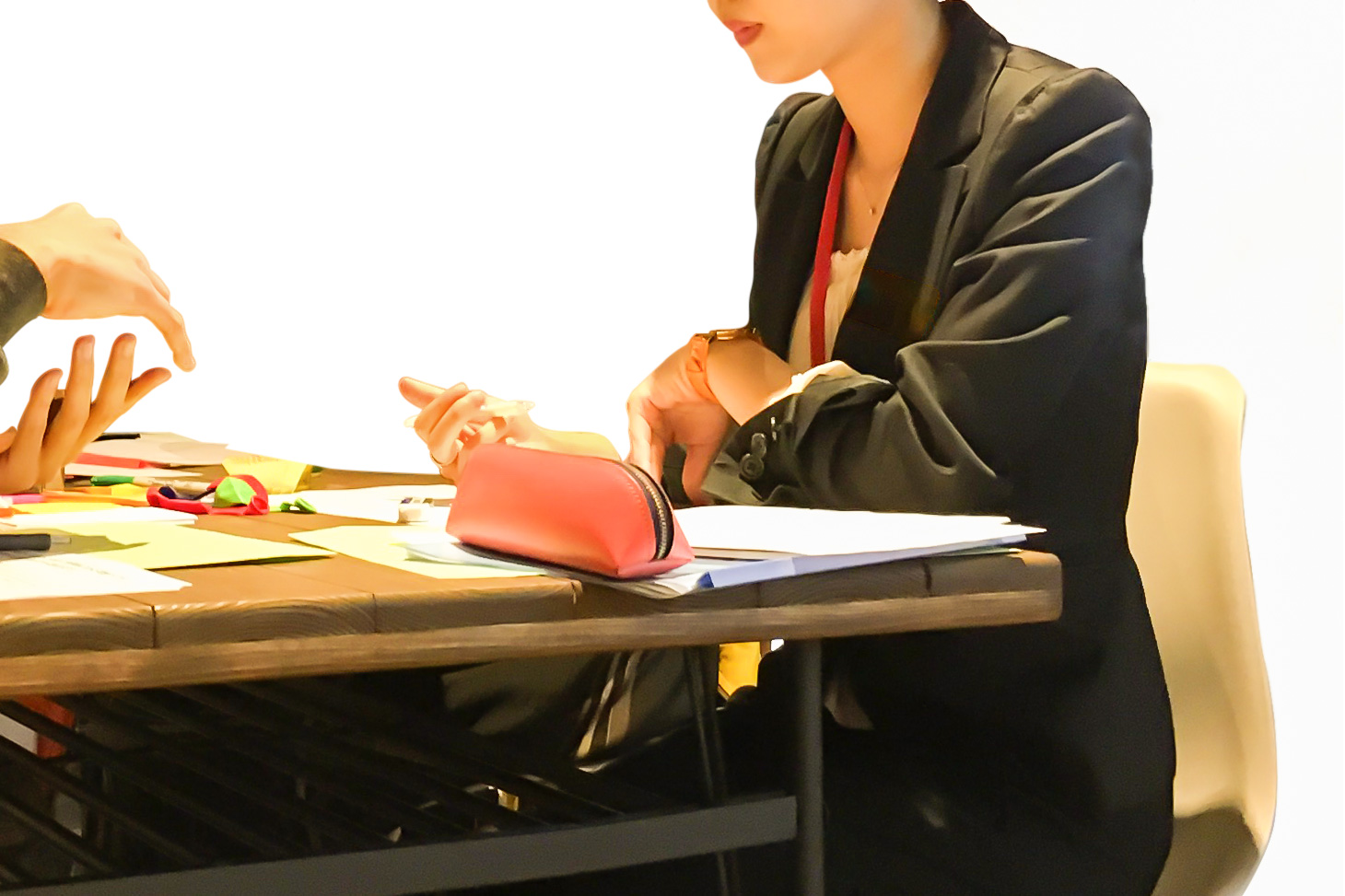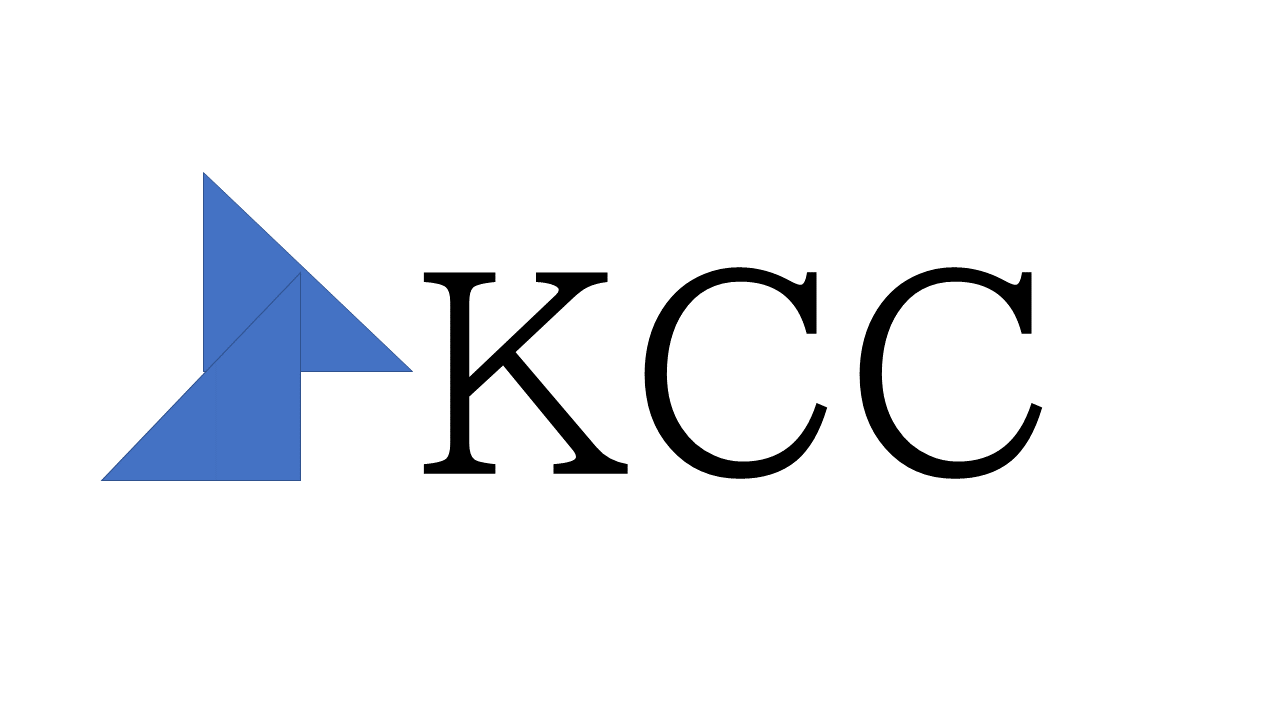前回の更新から1年以上経ってしました。1年以上経って、能登がメディアの話題に上ることも減っています(地元のメディアは依然として頻繫に取り上げていますが)。復興は進んではいるものの、能登がこの先どんな町になるかはわかりません。倒壊した建物や道路などを撤去・再建した後の能登の姿は思い描けないままです。もともと人口減少・流出に歯止めがかからなかった町なので、元に戻すことにはならないでしょう(元に戻しても、いずれも町はなくなります)。この課題については別途、考えるとして、今回そもそもこの連載の本旨であり目的であった「能登を振り返る」ことにフォーカスします。焦点を当てるのは能登の祭りです。
2日間にわたり、町を染める祭りの熱気。
私が生まれた町の祭りを紹介します。今、祭りというと町内会主催のイベントのようなものも少なくありません。今から30年ほどの前、社会科の教科書に「近年は神仏への感謝や豊穣への祈りを捧げることを目的としない、社会的祭り(という名称だった思います)が増えている」という記述がありました。そうした祭りの目的は「地域のつながりを作ること」だったと記憶しています。
当時、私は伝統的な祭りしか思い浮かべることができず、あの「祭り」以外にどんな祭りがあるのかと思いました。しかし、今となっては「祭り」というと、若い層を中心に社会的祭りを想像するかもしれません。中には、伝統的な祭りには参加したことがない人もいるのではないでしょうか。
能登の私の住んでいた町で行われていたのは、当然のことながら伝統的な祭りです。神社が起点となりますので、神様への祈りがささげられます。8月のお盆中に2日間にわたって繰り広げられました。今考えると、これはとてもすごいことではないかと思います。町全体が(といっても、2~300人程度の町ですが)、2日間にわたり祭り一色に染まるのです。その2日間は祭り以外のことをしている人はいないと言っても過言ではありません。それどころか、7月に入ると町の人たちは準備を始め、徐々に町全体が祭りに向かっていきます。地域が総出で準備をして、当日は総出で賑やかに騒ぎました。
小学生以上の子どもにも役割があって、当日まで祭りの準備を行い、当日は当事者として参加します。住民である限りは準備から強制参加です。選択権はなかったと思いますが、参加したくないという人はいなかったのではないかと思います。何しろ、年に一度の最大の楽しみなので。
「ハレ」の日の記憶。祭りの風景と地域コミュニティ。
「ハレ」と「ケ」という言葉がありますが、祭りはまさにハレの日、特別な日です。町全体が大変に盛り上がり、文字通りお祭り騒ぎとなります。家々は祭りのための装飾をします。住民は祭りの日だけしかしない格好をして、特別なごちそうも振る舞われました。遠方の親戚が訪ねてくることも少なくありません。その日しか会えないような人もいました。日常つまり「ケ」の日とは明確な区別があったのです。今でもハレというとあの能登の祭りを思い出します。
振り返ると、ああいう「祭り」が成り立っていたことに、時代性というか地域性を感じます。正直、今私の住んでいる町でこうした催しがあると言われると、かなりの抵抗を覚えます。祭り当日に町の中に滞在しているかも不明です。参加への強制はないでしょう。そうした地域的な強制や古い伝統がないからこそ、住めていると言えるかもしれません。
もちろん、ここで伝統の良し悪しを論じるつもりはありません。私は能登を離れた人間ですので、論じる立場にもないのです。お伝えしたいのは、今から一世代、30年前は、能登で地域を挙げての年中行事が成り立っていたということです。地域に子どもからお年寄りがいて、十分な時間を割ける人が大勢いたことは、祭りを成立させていた大きな要因の一つだと考えられます。伝統も引き継がれていました。子どもたちは子どもたちで年上の者から指導を受け、数年後には自分たちが指導する立場になるということが繰り返されていました(私はその流れを断った一人ですが)。
おそらく、当時は全住民参加型の年中行事が規模の大小を問わずあちこちで営まれていたはずです。その多くが、なくなるかなくなる寸前ではないかと推測されます。私のいた町から子どもはすっかりいなくなってしまいましたが、幸いなことに祭りを残そうという動きがあり、地域外の人たちに支えられています。
少し話はそれるかもしれませんが、都市部やベッドタウンなどでは、後から来た人間が伝統に深く関わることはあまり多くないと思います。だからこそ、気楽に住める。地域と関わろうが関わるまいがある程度の自由が許されます。一方、伝統ある地域への移住となると、伝統や習慣を受け入れる必要があるような気もします。そこに培われてきたものがあるのは間違いないからです。それを残す残さないはともかく、後から来た人が伝統を無視して新しい町を創る、と言い出すと、軋轢が生まれるのも無理のないことでしょう。とはいえ、伝統を知れ受け継ぐべきと、強制もできません。そこが難しいところでもあります。
これまであまり意識したことはなかったのですが、今自分が住んでいるところを含め、改めて地域について理解を深めないといけない、そう思いました。
あとがき
祭りにフォーカスして能登を振り返りました。今はもう地域の住民でもなんでもありませんし、足も遠のいていました。それでも、能登での生活を思うと、祭りのシーンが思い出されます。思い出すといつでも、不思議な感覚にとらわれます。なぜあの町は、あんなにエネルギーを持つことができたのだろうと思うからです。祭りの紹介ではないので、細かな内容は省きました。能登のある町の風景、一つのシーンとして受け止めていただければ幸いです。