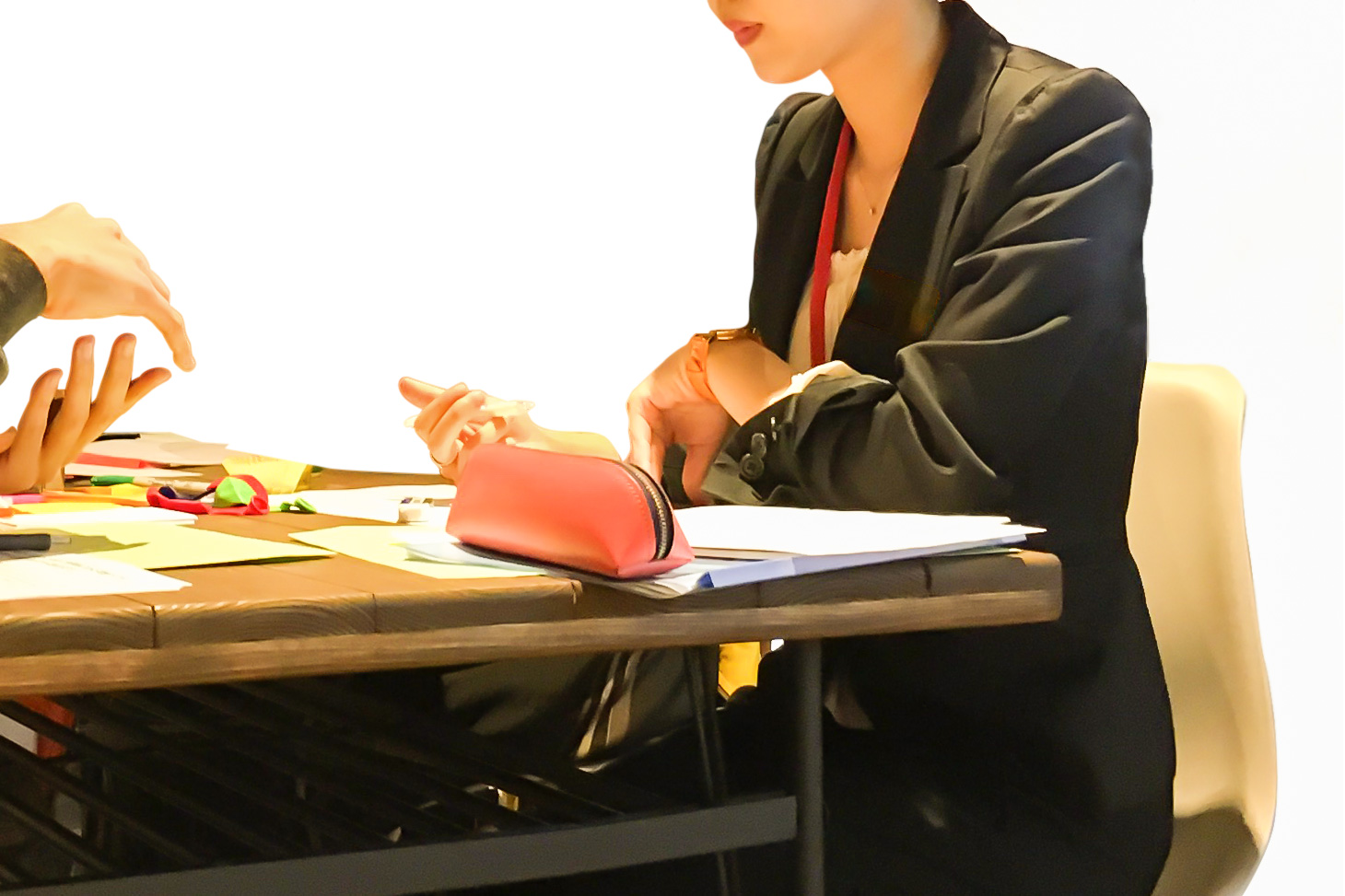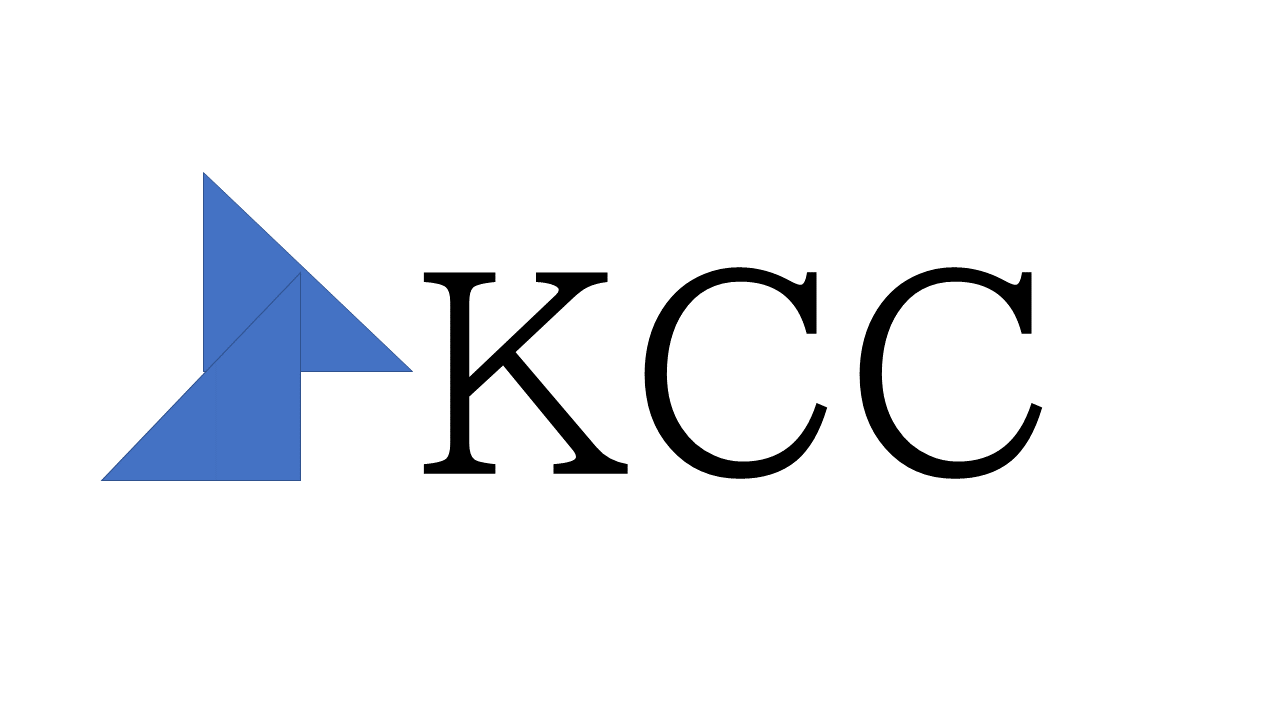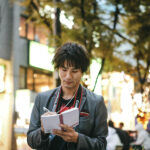1年後、あなたの隣の同僚は、AIをまるで優秀なアシスタントのように使いこなし、定型業務を瞬時に終わらせ、社員との面談や戦略立案に多くの時間を使っているかもしれません。一方のあなたは?
AIは使えて当たり前、特別なことではない、という未来がもうそこまできています。
「AIは難しそう」と感じるすべての人事担当者の方へ。この記事では、AIを”最強のパートナー”に変えるために、今すぐ「AI慣れ」すべき3つの理由と、今日からできる簡単なアクションプランをご紹介します。
読み終えるころには、漠然とした不安が、「これなら自分にもできる」という確信と、未来へのワクワクに変わっているはずです。
まずはなぜ「AI慣れ」が必要なのか。理由を解説します。
目次
理由1:日本の「AI活用の遅れ」が、企業の競争力低下に直結する
「日本はAI活用で遅れている」と漠然と聞いたことがあるかもしれません。その遅れは今や無視できないレベルに達しています。
マイクロソフト社の調査によると、日本のビジネスパーソンのうち、業務で生成AIを活用している割合はわずか32%。これは調査対象19カ国の中で最も低く、世界平均の75%を大きく下回る結果でした。
(出典:Microsoft Work Trend Index 2024など)
海外のビジネスパーソンがメール作成や情報収集にAIを駆使し、生産性効率を上げている間、日本国内では多くの定型業務を依然として手作業で行っているのが現状です。
早稲田大学大学院の入山章栄教授は「AIはインターネットのようなインフラになる。使えるのが当たり前で、AIを使えたからといって『イケてる』とはならない。AIを使えないと『お終い』くらいの感覚」と述べています。
今はPCやインターネットが使えなければ仕事にならない場面が多くあります。ビジネスそのものが成り立たないこともあるでしょう。同様に、数年後にはAIを使いこなせないことが、個人の評価だけでなく、企業全体の競争力に直接影響する、もっというと業界の存亡にも関わる時代が目前に迫っているのです。
理由2:人事の仕事は「人にしかできない業務」へシフトしていく
「AIに仕事を奪われる」という不安を耳にすることもあります。本当でしょうか。「仕事の質が変わる」が正確かもしれません。少なくとも人事の領域では「AIに任せるべき仕事と、人にしかできない仕事が明確になり、後者の価値が飛躍的に高まっていく」と考えられるのです。
AIが得意なのは、膨大なデータを処理・分析し、最適なパターンを見つけ出すことです。履歴書のスクリーニングや勤怠データの集計など「正解がある」「効率化できる」業務は、今後ますますAIに置き換わっていくでしょう。一方で、AIではどうしてもできないこと、人が行わなければならないことがあります。
では、AI時代に人事担当者の価値が発揮される「人にしかできない仕事」とは何でしょうか。それは、共感、創造性、倫理観が求められる、より人間的な業務です。
具体的には、以下の5つの領域が挙げられます。
AIはキャリアパスを提案できても、社員一人ひとりの言葉にならない悩みや不安に寄り添うことはできません。1on1やキャリア面談などを通じて、相手の表情や声のトーンから真意を汲み取り、「この人になら本音で話せる」と信頼関係を築くことは、人間にしかできない最も重要な仕事の一つです。
AIは従業員サーベイの結果を分析し、組織の課題を特定することはできます。しかし、その結果をもとに「我々は社会に対してこんな価値を提供したい。だから、社員にはこうあってほしい」とビジョンを語り、社員の心を動かし、組織の一体感を醸成するのは、熱意を持った人間の役割です。
採用プロセスでAIはスキルや経歴のマッチング精度を飛躍的に高めてくれます。しかし、候補者の価値観や人柄が自社の文化に本当にフィットするかを読み取るのは困難でしょう。チームに新しい化学反応をもたらしてくれるか、といった言語化しきれない「空気感」を見極めるのは人間だからできること。さらに、最終的な意思決定を下すのも重要な役割であり、それを行うのは経験と感性を持った人間なのです。
ハラスメントやメンタルヘルス不調など非常にデリケートな問題に対応する際、法律や規則のデータだけで判断することはできません。当事者の感情に深く配慮し、プライバシーを守りながら、個別最適な解決策を粘り強く模索します。高度な倫理観と人間理解が求められます。
AIは人材をデータを見て分析します。ここまでAIの役割です。この後は人間がデータを基に「なぜ今、この人事戦略が必要なのか」「この人材配置が、3年後の事業成長にどう繋がるのか」というストーリーを構築し、経営陣を説得し、事業を動かします。これは、データを未来への構想に転換する、人間の創造性と戦略的思考そのものです。
このように、AIは私たちから仕事を奪うのではありません。私たちを「管理業務」から解放し、本来あるべき「人と組織の可能性を最大化する」創造的な仕事に集中させてくれる強力なパートナーとなるのです。

理由3:「AIを使えない」ことが、そのまま経営リスクになる
もし、あなたの会社だけがAIを使わなかったら、どのような未来が待っているでしょうか。
採用競争力の低下: 競合他社がAIで優秀な人材を素早く獲得する一方、自社は膨大な応募書類の確認に忙殺され、優秀な人材を取り逃がし続ける。
データに基づかない意思決定: 勘と経験に頼った人員配置や評価には限界がある。好ましくない恣意的判断が入り込むこともしばしば。この結果、従業員のエンゲージメントが低下し、優秀な社員から見切りをつけられてしまう。
戦略人事への乗り遅れ: 日々のオペレーション業務に忙殺され、経営課題の解決に貢献する「戦略人事」への変革がいつまでも進まない。
これらは、もはや単なる「非効率」では済まされません。企業の存続に関わる「経営リスク」と言えるでしょう。
AIに触れよう!人事のための「AI慣れ」3ステップ
ここまで読んで、「重要性は分かったけれど、何から始めれば……」と感じた方も多いはずです。専門家になる必要はありません。大切なのは、まず「触れてみること」。「AI慣れ」とは、AIを日常業務の中で自然に使いこなす感覚を身につけることです。専門知識よりも、まずは「触れてみる」ことを大事にしましょう。
今日から始められる、簡単な3ステップをご紹介します。
ChatGPTやGeminiといった生成AIに、メールの文面や求人票のキャッチコピー作成を手伝わせてみましょう。「新卒採用向けの、ユニークな会社説明会の企画を5つ提案してください」――こんな風に話しかけるだけで、AIはあなたの新しいアイデアの壁打ち相手になってくれます。
Webで「HRテックカオスマップ」と検索し、どんなサービスがあるのかを眺めてみましょう。きっと「こんな面倒な作業、ツールで解決できるんだ!」と発見があるはずです。
もし「面接の日程調整がいつも大変だ」という課題があれば、AI日程調整ツールの無料トライアルを試すなど、一部の業務で小さく試してみましょう。
もし業務に使うことに抵抗があるのなら、まずは気軽に調べものや雑談を行ってみるのも一つの手です。「AIってこんなに気軽に使えるんだ」と感じることが、最も重要な第一歩です。
まとめ
AIはもはや、一部の専門家だけのものではありません。これからのビジネスを支える社会インフラです。特に、企業の「人」と「組織」を扱う人事担当者こそ、AIをいち早く味方につけることで、自身の業務を効率化し、会社の成長に貢献する戦略的な価値を発揮できます。AIを駆使する人事が、これからの企業を支える存在になります。
ただし、ここで最も大切なことを忘れてはいけません。AIはあくまで人事の業務を助けてくれるツールに過ぎないということです。AIを使いこなすこと自体が、人事の役割になるのではありません。AIを活用して生まれた時間で、いかに深く社員一人ひとりと向き合うか。人事の本質は、いつの時代もそこにあるはずです。その点をお忘れなきように。
AIを駆使することで、企業の未来を構想し、動かす「戦略の担い手」へと変貌を遂げられます。まずは今日のメール作成から、AIをあなたの「相棒」にしてみませんか。